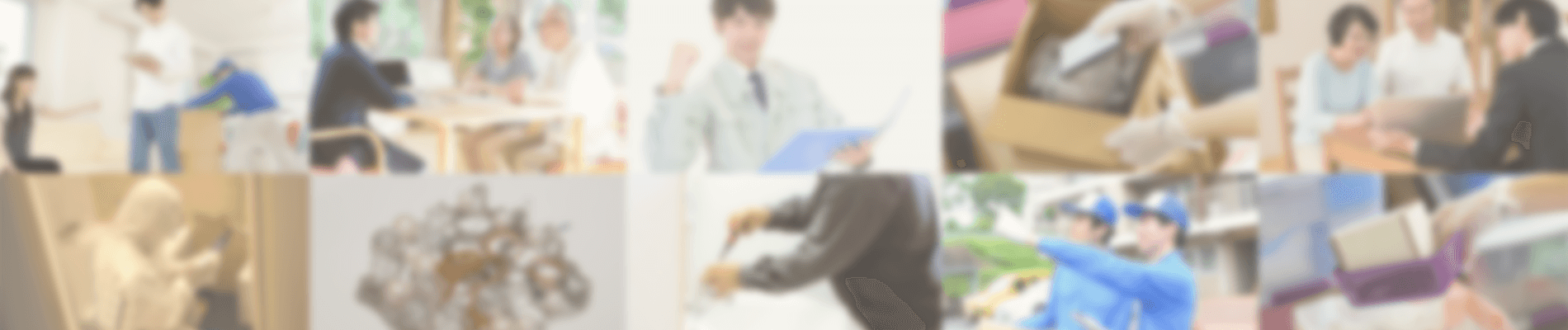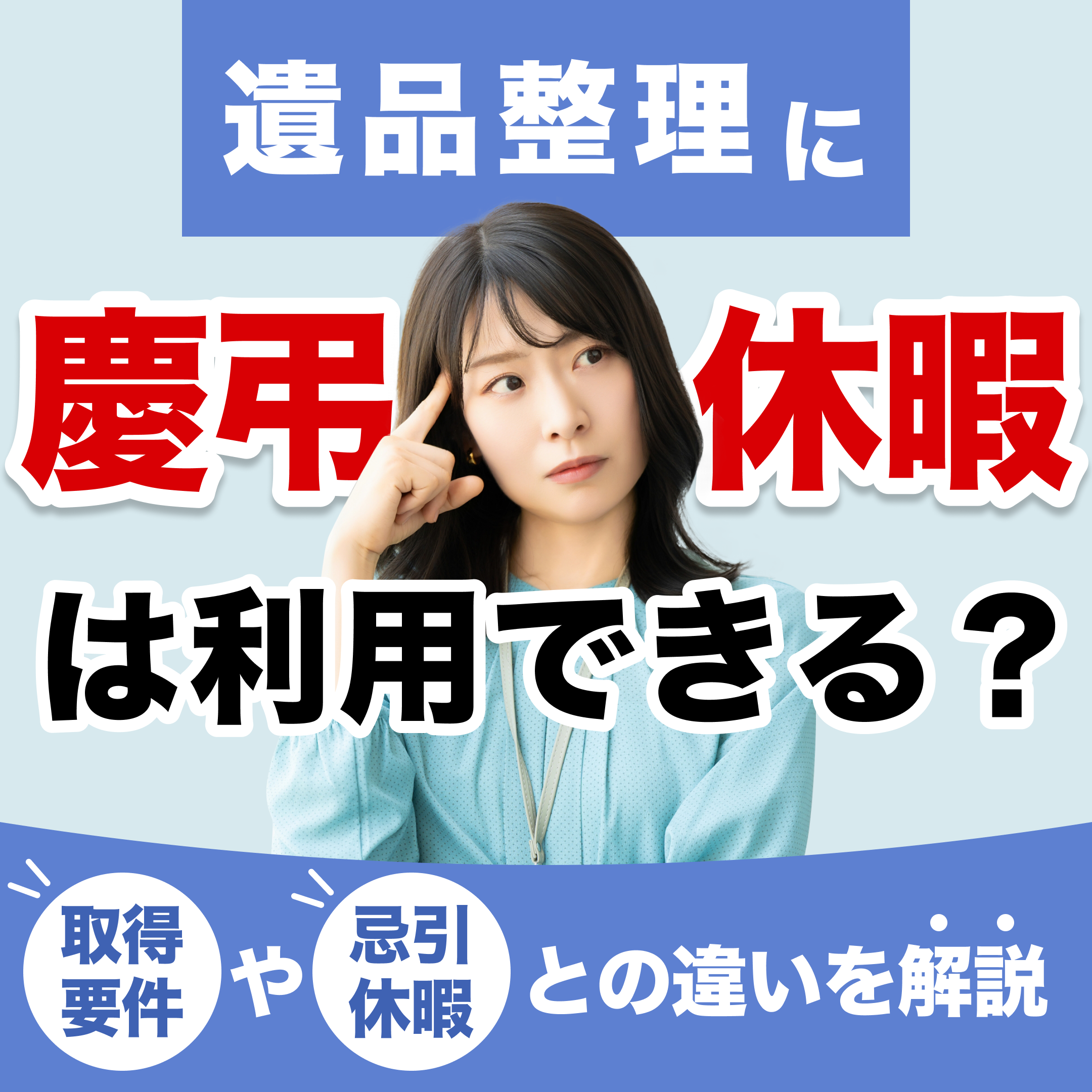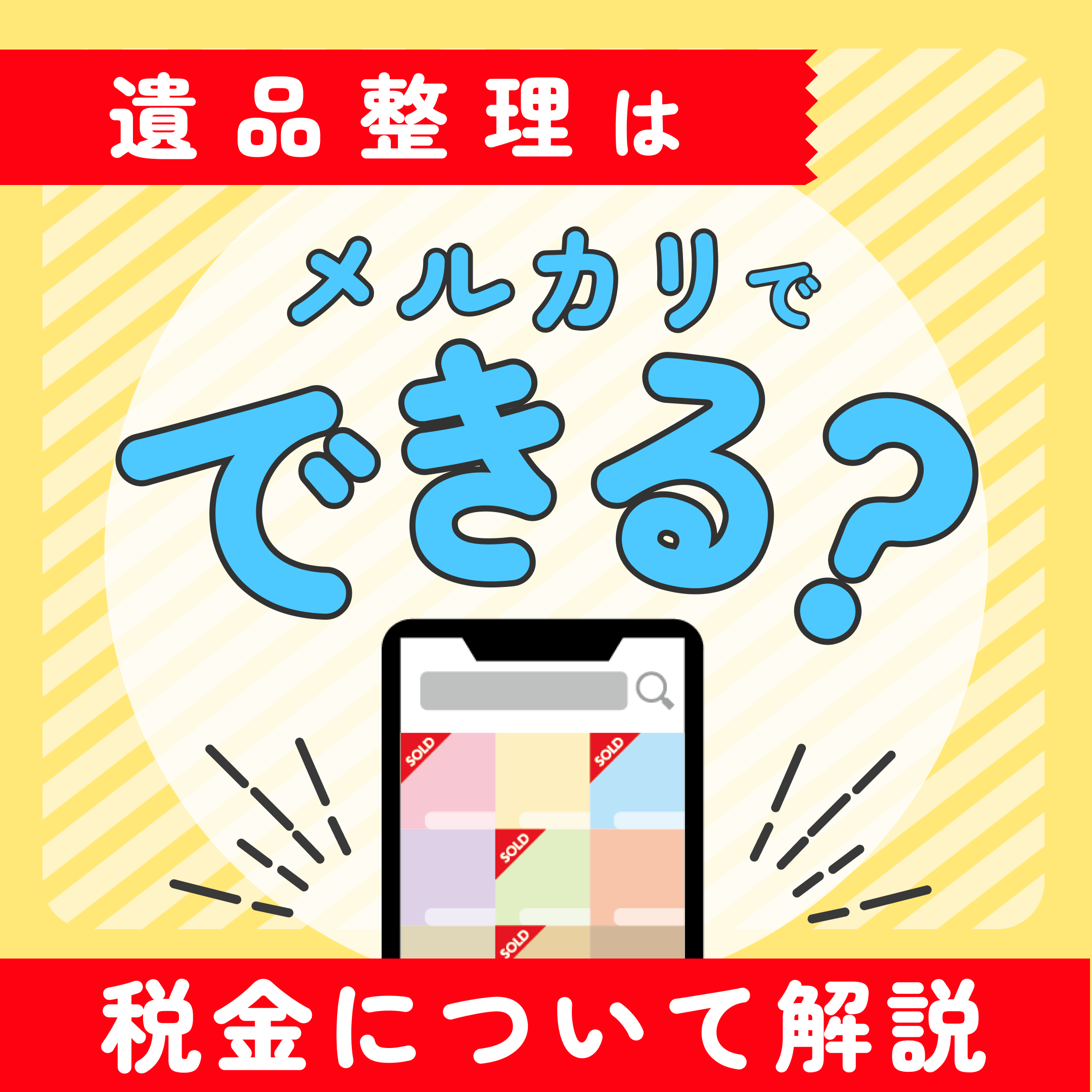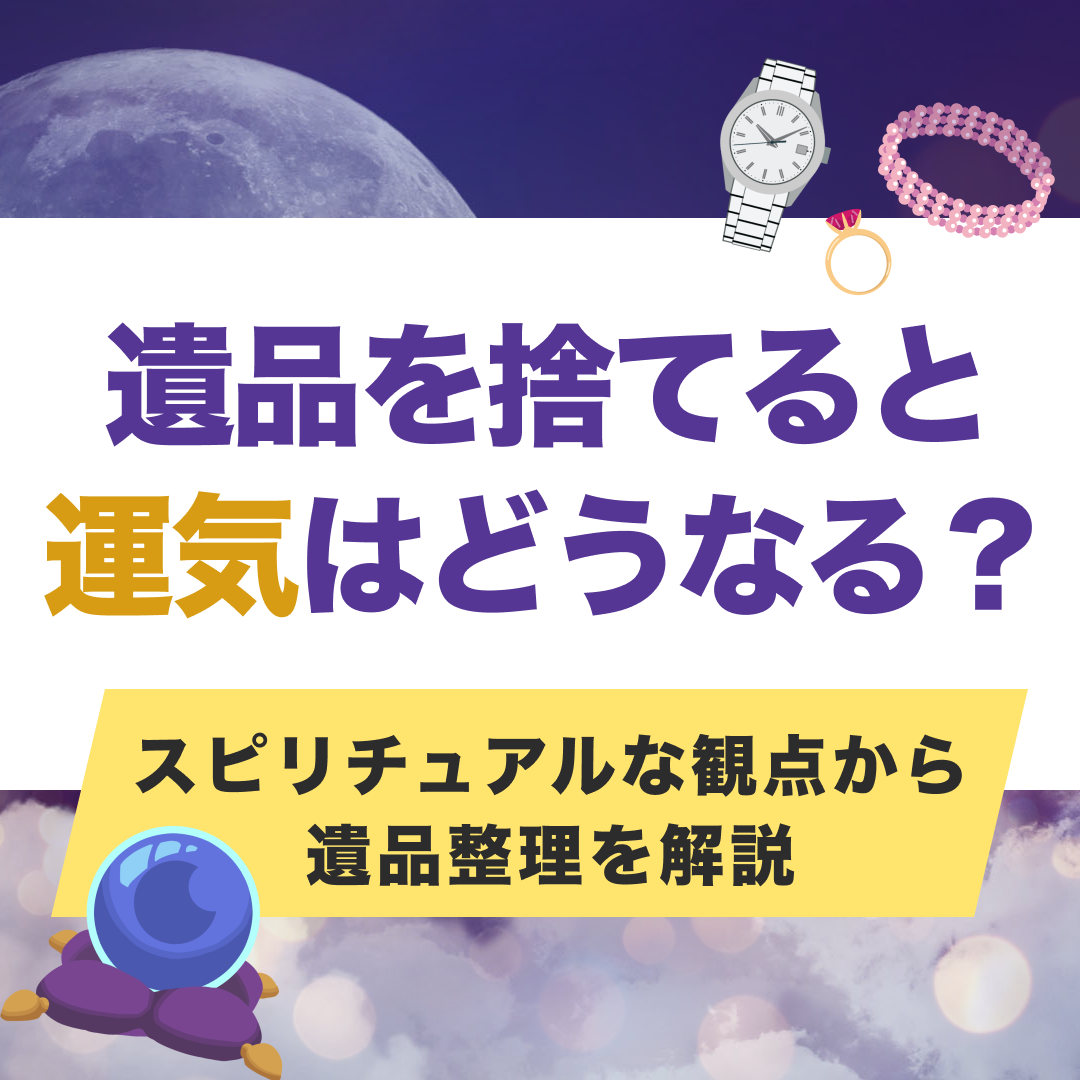遺品整理で遺骨が見つかったら?|供養や納骨など詳しく解説
![]() 最終更新日:2025.05.19
最終更新日:2025.05.19

遺品整理は故人との思い出を整理する大切な時間ですが、予期せぬ形で遺骨が見つかることもあります。このような状況では、どのように遺骨を取り扱い、供養や納骨を進めていけば良いのでしょうか。
この記事では、遺骨を整理する手順や法的な注意点、費用について具体的に解説します。遺品整理中に見つかった遺骨を適切に供養し、故人や遺族にとって最善の方法を見つける一助としてください。

こんにちは。おうち整理士の榛田(はりた)です。今回は、遺品整理で遺骨が見つかった時の対応や解決策を詳しく解説します。
目次
遺品整理中に遺骨を発見したときの初期対応

遺品整理を進める中で遺骨を発見した場合、まずは落ち着いて対処することが大切です。突然の発見に戸惑うかもしれませんが、適切な手順を踏むことで、故人にとっても遺族にとっても最善の対応ができます。身元の確認から一時的な保管まで、最初に行うべき事柄について説明します。
家での一時的な保管方法
遺品整理中に遺骨を家で一時的に保管する場合、まず、遺骨が納められた骨壺や容器を、直射日光が当たらず湿気の少ない涼しい場所に置きましょう。湿気は遺骨の状態を損なう可能性があるため、特に注意が必要です。
一般的には、四十九日までは後飾り祭壇に安置することが多いですが、その後も引き続き自宅で保管することも法律上問題ありません。
後飾り祭壇は、白い布をかけた台の上に骨壺を置き、線香立てや供物などを供えるもので、仏間がない場合はリビングなどに置くこともできます。
小さい骨壺に移し替えて、より手軽に自宅で供養することも可能です。遺骨を自宅に置くこと自体は違法ではありませんが、親族の理解を得ておく必要はあります。
→あわせて読みたい
「家の祭壇を片付けるタイミングは3つ|宗教ごとの違いを解説します」
遺骨の身元を確認する
遺品整理で見つかった遺骨が誰のものか不明な場合は、身元を確認する手順を踏みます。
まず、骨壺や袋に記載されている名前や日付などの情報を確認しましょう。骨壺の蓋の裏などに情報が書かれていることもあります。
もしそれだけでは特定できない場合は、故人の遺品の中から位牌や戒名、写真、遺影など、故人に関連する手がかりを探します。これらの情報から故人の身元が判明することもあります。
それでも身元が分からない場合は、故人の親族や知人、生前お世話になった病院や施設に連絡を取りましょう。特に、古い遺骨で祖父母など面識のない故人のものである可能性も考えられます。
身元が特定できない場合は、遺品整理業者に相談することも一つの方法です。遺品整理業者は、このようなケースの対応経験がある場合があるため、専門的なアドバイスやサポートを受けられる可能性が期待できます。
→あわせて読みたい
「遺品整理を業者に依頼するメリット6つ|どんな業者を選ぶと良いかも解説」
遺骨の取扱いの流れ

遺骨の取扱いを円滑に進めるための流れを理解しておきましょう。
遺族や関係者への連絡方法
遺品整理で遺骨が見つかった場合、速やかに遺族や関係者に連絡を取り、状況を共有することが重要です。特に故人の配偶者や子供、両親などの近親者には、最初に見つかった経緯や遺骨の状態などを丁寧に伝えるようにします。もし遺言書などで遺骨の取り扱いに関する故人の意思が示されていれば、その内容も共有し、遺族の意向を確認する際の参考にできます。
連絡は電話や直接会って話すのが望ましいですが、難しい場合は手紙やメールなども検討しましょう。複数の遺族がいる場合は、今後の手順を円滑に進めるために、一度集まって話し合う機会を設けることも有効です。
祭祀承継者の決定と供養の意思確認
遺骨が見つかったら、誰が祭祀承継者となるかを明確にし、遺骨の供養に関する意思を確認する必要があります。
祭祀承継者とは、お墓や仏壇、遺骨などの祭祀財産を受け継ぎ、管理・供養を行う人のことです。故人が遺言で祭祀承継者を指定している場合、その指定が優先されます。遺言がない場合は、故人の生前の意思や地域の慣習、親族間の話し合いによって決定されることが一般的です。遺族全員で協議し、誰が責任を持って遺骨の供養を行うかを決めましょう。
祭祀承継者が決まったら、その後の供養方法について具体的に検討を進めます。自宅での手元供養を希望するのか、お墓への納骨、永代供養、散骨など、様々な選択肢の中から、故人の遺志や遺族の思いに沿った方法を選びます。もし遺族間で意見が分かれる場合は、専門家や親族間の話し合いをサポートする第三者に相談することも検討できます。
遺骨の供養方法4つ

遺骨の供養方法は一つではなく、多様な選択肢があります。それぞれに特徴や費用、手順が異なるため、事前に押さえておきましょう。
お墓に納骨する
遺骨をお墓に納めることは、最も一般的で伝統的な供養方法の一つです。多くの場合、先祖代々のお墓や、新たに建立した個人墓、夫婦墓などに納骨されます。
お墓に納骨する際には、墓石の下にあるカロートと呼ばれる納骨室に骨壺を安置します。納骨式と呼ばれる儀式を執り行うことが一般的で、僧侶にお経をあげてもらい、遺族や親族が立ち会います。墓石に故人の名前や没年月日などを彫る作業も伴います。
既存のお墓に納骨する際、すでに多くの遺骨が納められている場合は、古い遺骨を別の場所に合祀したり、骨壺から出して遺骨だけを納めたりすることもあります。祖父母など、面識のない故人の遺骨でも、親族の同意があれば代々のお墓に納骨することは可能です。
新しいお墓を建てる場合は、墓地の選定から墓石の建立まで、時間と費用がかかるため、計画的に進める必要があります。お墓への納骨は、お参りの場所が明確になるメリットがありますが、墓地の管理費や維持費がかかるという点も考慮する必要があります。
合祀墓に納骨する
合祀墓(ごうしぼ)は、複数の人の遺骨を一緒に埋葬するお墓で、永代供養墓の一種として利用されることが多いです。遺骨を骨壺から出して、他の方々の遺骨と共に一つの場所に納める形式が一般的で、個別の墓石はありません。
合祀墓での納骨は、個別にお墓を建てるよりも費用を抑えられる点が大きな特徴です。また、お墓の管理や継承の心配がないため、お墓の後継者がいない場合や、子孫に負担をかけたくないという場合に選ばれることがあります。
合祀墓への納骨を希望する場合、まず霊園や寺院に申し込みを行い、必要な手続きを進めます。納骨時には、他の遺骨と混ざるため、一度納めると後から特定の遺骨を取り出すことは難しくなります。多くの合祀墓では、定期的に合同供養が執り行われ、無縁仏となる心配がないため、安心して任せられるでしょう。
手続きの際には、埋葬許可証などが必要となりますので、事前に確認しておきましょう。
納骨堂で供養する
納骨堂は、遺骨を屋内の施設に安置する供養方法です。都市部に多く見られ、様々な形式があります。ロッカー型、仏壇型、自動搬送型などがあり、それぞれのタイプによって特徴や費用が異なります。
納骨堂では、骨壺のまま個別のスペースに安置することが一般的で、お参りの際にはその場所で手を合わせることができます。永代供養付きの納骨堂も多く、管理や供養を施設に任せられるため、お墓の継承者がいない場合や遠方にお墓がある場合に選ばれることがあります。一定期間個別で安置した後、合祀墓に移される契約になっている場合もあります。
納骨堂は屋内にあり、天候に左右されずにお参りできるというメリットや、駅から近いなどアクセスが良い場合が多いのも特徴です。費用は形式や立地、契約期間によって幅がありますが、個別にお墓を建てるよりも費用を抑えられる傾向にあります。年間管理費がかかる場合もあるため、契約内容をよく確認しておきましょう。
散骨や樹木葬で供養する
散骨や樹木葬は、自然に還ることを目的とした新しい供養方法として近年注目を集めています。
散骨は、遺骨を粉末状にして海や山などに撒く方法です。お墓を持たずに故人を自然に還したいと願う方に選ばれます。海洋散骨が一般的ですが、山林への散骨や、一部を手元に残して供養する手元供養と組み合わせることも可能です。散骨を行う際には、法的なルールを守り、周囲への配慮が必要です。許可なく私有地や公共の場所に散骨することはできません。
樹木葬は、墓石の代わりに樹木を墓標として遺骨を埋葬する方法です。公園型と里山型があり、管理された敷地内に個別に埋葬する場合や、合祀の形式もあります。樹木葬は、自然の中で眠りたいという故人の希望を叶えつつ、お参りする場所があるという点が特徴です。
散骨も樹木葬も、従来の石のお墓に比べて費用を抑えられる傾向にあり、永代供養が付いている場合も多いです。どちらの方法も、一度行うと遺骨を元に戻すことが難しいため、遺族や関係者と十分に話し合いましょう。
→あわせて読みたい
「仏壇を処分する方法4つと費用の相場|遺品整理のプロが教える注意点」
遺骨の取り扱いで注意すべき法律やルール
遺品整理で見つかった遺骨の取り扱いには、いくつかの法律やルールが存在します。これらの決まり事を理解せずに進めると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。事前に確認しておきましょう。
遺骨の勝手な処分に関する禁止事項
遺骨を勝手に処分することは法律で禁止されています。「墓地、埋葬等に関する法律」により、遺骨を埋葬できる場所は都道府県知事の許可を得た墓地に限定されています。そのため、自宅の庭や私有地に無許可で埋葬することや、ゴミとして廃棄することは違法行為にあたります。
刑法第190条「死体等遺棄罪」では、遺骨を遺棄した者に対して罰則が定められています。遺品整理中に見つかった遺骨であっても、故人の大切な一部であり、適切な手続きを踏んで供養または埋葬する必要があります。
もし遺骨の扱いに困った場合は、勝手に処分したりせず、自治体の担当部署や専門業者、寺院などに相談するようにしましょう。法に基づいた正しい手順で進めることが、故人の尊重と遺族の安心につながります。
家で遺骨を弔う際の供養の仕方
遺骨を必ずしも屋外のお墓に納めなければならないわけではありません。自宅で遺骨を保管し、日々供養することも可能です。近年は、核家族化やライフスタイルの変化に伴い、自宅で故人を偲びたいという遺族の意向から、手元供養を選ぶ方が増えています。家で遺骨を弔う様々な供養の仕方についてご紹介します。
家庭でできる供養の方法
遺骨を自宅で供養する方法には、いくつかの選択肢があります。
最も一般的なのは、骨壺を自宅に安置し、お仏壇や手元供養壇などに飾って日々手を合わせる方法です。従来の大きな仏壇がない現代の住居事情に合わせて、コンパクトなミニ仏壇や、シンプルでおしゃれなデザインの手元供養壇なども多く販売されています。
遺骨の一部を小さなミニ骨壺やペンダント、指輪などのアクセサリーに納めて身近に置いておく「手元供養」も人気があります。これにより、いつでも故人を偲び、語りかけることができます。また、遺骨を加工してダイヤモンドにするなど、新しい形の供養方法も登場しています。
永代供養を利用する場合
永代供養は、遺族に代わって寺院や霊園が長期間にわたり遺骨の管理・供養を行う方法です。お墓の承継者がいない場合や、遠方に住んでいてお墓参りが難しい場合などに選ばれることが多いです。
永代供養には、他の人の遺骨と一緒に埋葬される合祀墓や、一定期間個別に安置された後に合祀される集合型や個別型など、様々な形式があります。納骨堂も永代供養の一つの形として利用されることがあります。永代供養を利用することで、将来にわたって遺骨が無縁仏になる心配がなく、管理の手間もかかりません。
永代供養を検討する際は、複数の施設を比較し、費用や供養の内容をよく確認しましょう。
納骨や供養の選び方と費用の目安
遺骨の納骨や供養の方法を選ぶ際には、様々な要素を考慮する必要があります。故人の遺志や遺族の希望はもちろん、費用や管理の手間、お参りのしやすさなどを総合的に判断し、家族にとって最適な方法を選択することが大切です。それぞれの納骨・供養方法にかかる費用の目安を知っておけば、比較検討する上で役立ちますよ。
納骨方法ごとの費用比較
納骨方法によって費用は大きく異なり、一般的には以下の表のようになります。
| 納骨方法 | 費用 |
|---|---|
| 個人墓(永代供養墓) | 約200万円程度 |
| 合祀墓 | 数万円〜30万円程度 |
| 納骨堂 | 10万円〜150万円程度 |
| 集合型永代供養墓 | 20万円〜60万円程度 |
| 散骨 | 数万円〜30万円程度 |
| 樹木葬 | 20万円〜100万円程度 |
最も費用がかかるのは、一般的なお墓を建立して納骨する方法で、墓地永代使用料や墓石代、工事費などを合わせると、全国平均で約200万円程度が相場と言われています。契約時に永代供養料を一括で支払うケースが多く、年間の管理費がかからない場合がほとんどですが、個別安置期間中は管理費が必要な場合もあります。
一方、合祀墓に納骨する場合、費用は比較的安価で、数万円から30万円程度で済むことが多いです。
納骨堂を利用する場合の費用は、形式によって幅があり、ロッカー型や位牌型は比較的安価ですが、仏壇型や自動搬送型は高額になる傾向があり、0万円から150万円程度とされています。
集合型永代供養墓の場合は、一人あたり20万円から60万円程度が目安となることもあります。
散骨や樹木葬も、個別にお墓を建てるより費用を抑えられる場合が多く、散骨は業者に依頼すると数万円から、樹木葬は形式によって20万円から100万円程度が目安となるようです。
これらの費用はあくまで目安であり、地域や施設によって変動するため、複数の選択肢を比較検討し、詳細な見積もりを取っておきましょう。
供養プランの選び方のポイント
供養プランを選ぶ際は、いくつかのポイントを考慮しましょう。
まず、最も大切なのは故人の遺志を尊重することです。もし遺言や生前の話し合いで故人の希望が分かっていれば、それに沿った方法を検討しましょう。
次に、遺族の意向やライフスタイルに合った方法であるかを確認します。お墓参りを重視したいのか、管理の手間を省きたいのか、自宅で供養したいのかなど、遺族で話し合い希望を明確にしましょう。
また、費用も重要な判断材料となります。それぞれの供養方法にかかる費用を比較し、無理のない範囲で選択することが必要です。永代供養を検討する場合は、将来的な管理や供養の内容、契約期間なども確認しておきましょう。宗教や宗派による制約がある場合もあるため、事前に確認が必要です。
複数の供養方法を組み合わせることも可能です。例えば、一部の遺骨を手元供養し、残りを散骨するという選択もできます。家族や親族間で十分に話し合い、納得のいく供養方法を選べば、故人を偲びつつ、遺族が前向きに生きていく糧となります。
まとめ
遺品整理で遺骨が見つかることは、予期せぬ出来事かもしれませんが、落ち着いて適切な手順を踏むことが大切です。
もし対応に困る場合は、遺品整理業者や専門機関に相談することも有効です。家族にとって最善の方法を選び、故人を偲び、供養することで、遺族は心の整理をつけることができるでしょう。
わたしたちおうち整理士でも遺品整理を行なっています。遺骨の適切な処理についてもご相談いただけます。遺品整理士も在籍しているため安心してお任せいただけますよ。
お見積り
出張費
キャンセル
0円
即日お見積り&作業!実績多数!
まずはお気軽にお電話ください。
通話無料!営業時間 9:00~19:00/年中無休
![]() 0120-769-737
0120-769-737

![]() 受付時間外はメールでご相談ください
受付時間外はメールでご相談ください
[ 24時間365日受付 ]メールで相談する

これまでにおうち整理士で700件以上の遺品整理を担当。特殊清掃、リフォーム、骨董品買取など幅広い経験を重ねた上で知識を取得し、お客様に寄り添った仕事をモットーとしている。一般社団法人 遺品整理士認定協会「遺品整理士」を所持。