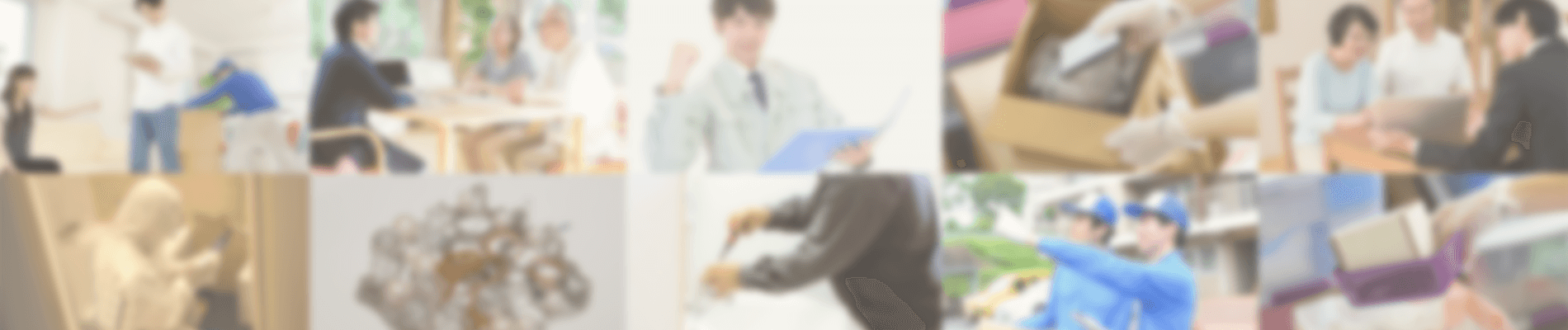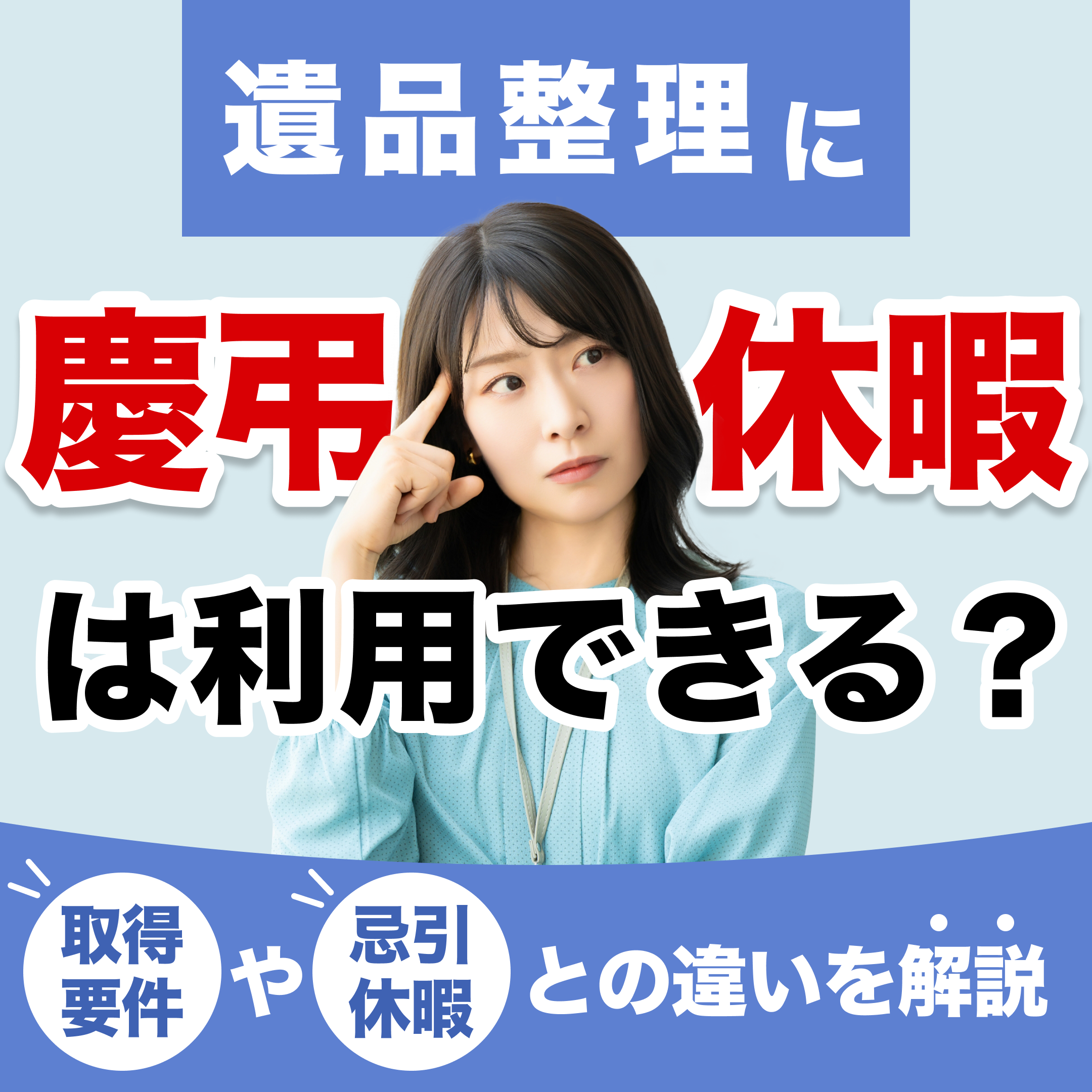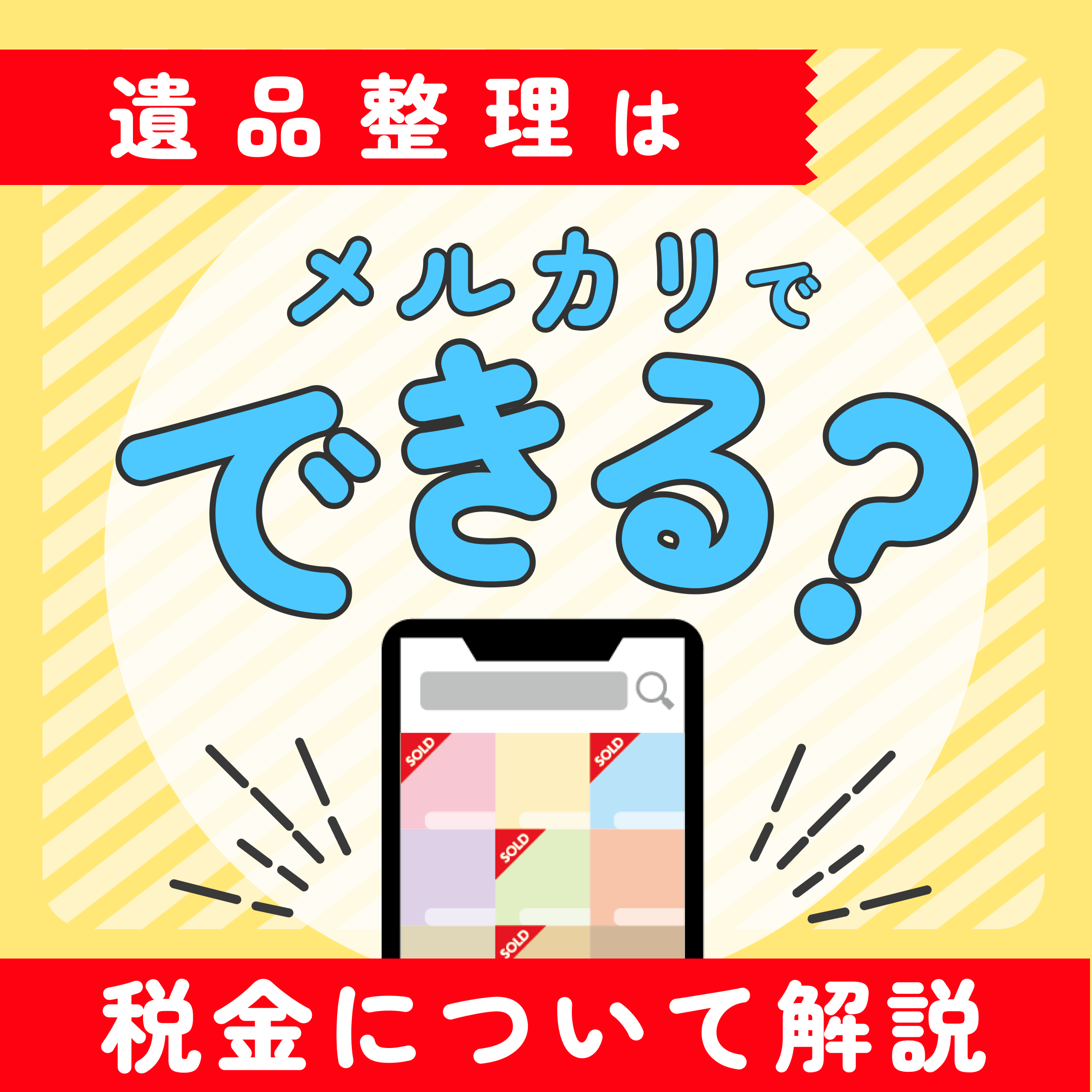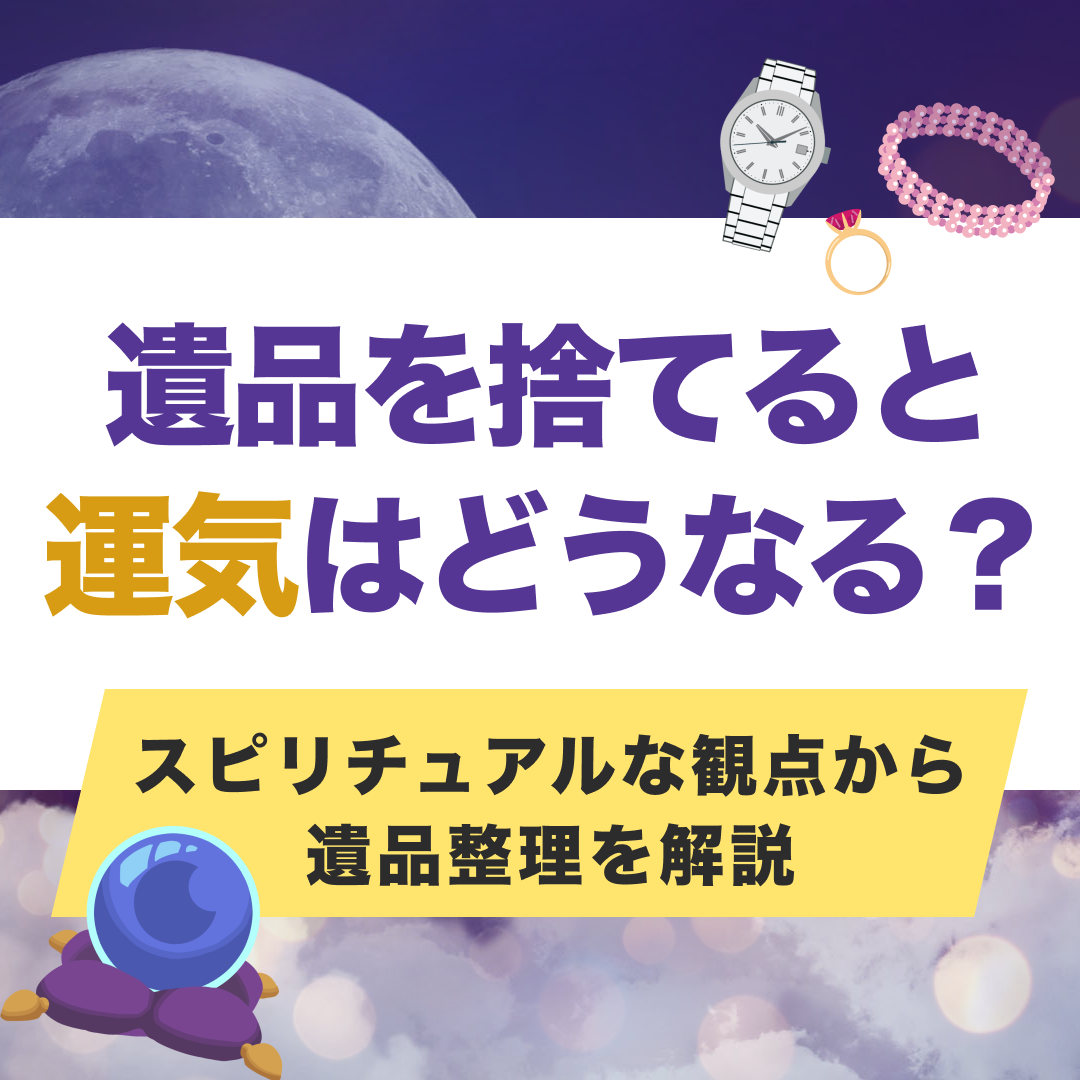形見分けはいつすべき?遺品整理のプロが教えるマナーと注意点
![]() 最終更新日:2025.06.09
最終更新日:2025.06.09
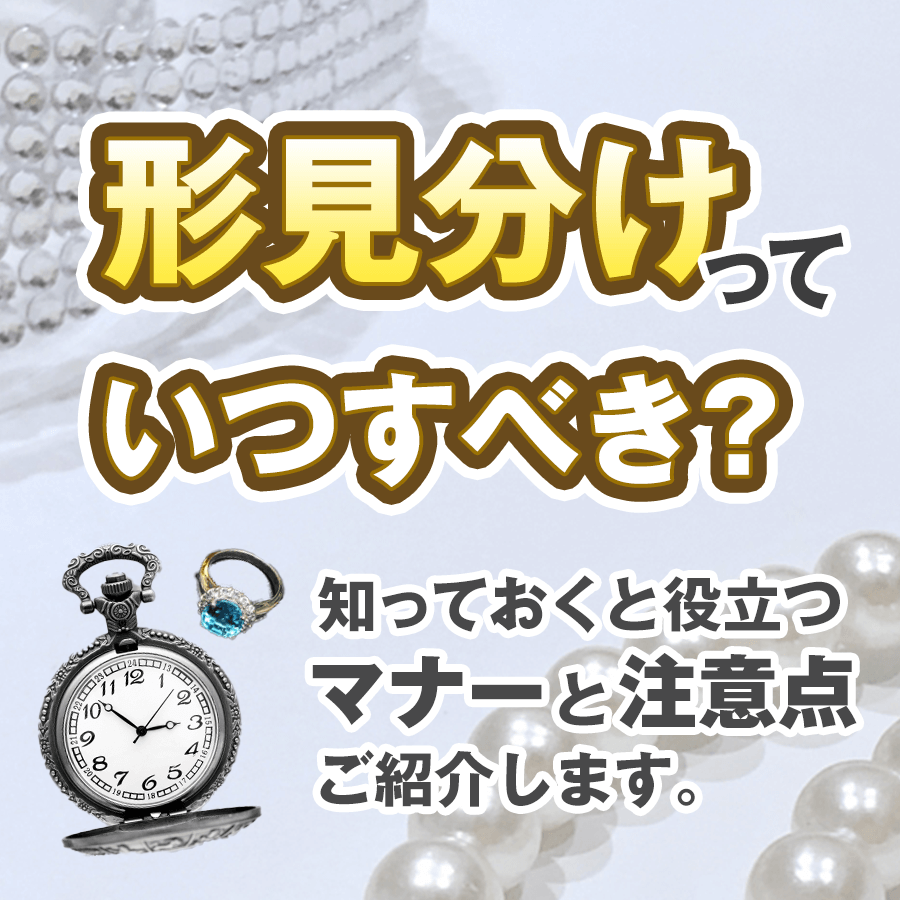
故人が愛用していた品物を、友人や親戚に分ける「形見分け」。言葉は聞いたことがあっても、適切な時期やマナーを知っている人は少ないのではないでしょうか。
今回は遺品整理のプロが形見分けをするのに良いタイミングや形見分けの方法、知っておいたほうがいいマナーをご紹介します。

こんにちは。おうち整理士の榛田(はりた)です。今回は、形見分けのマナーやタイミング、分ける時に知っておきたい注意点について、遺品整理のプロである私がご紹介します。
目次
形見分けとは

形見分けとは、故人が生前に愛用していた品物や思い出の品を、遺族や親しい友人・知人に分け与える日本の習慣です。故人を偲び、思い出を共有する意味合いがあります。
また、形見分けは原則として財産的価値の低いものに対し行われます。
形見分け・遺品整理・遺産分割の違い
形見分け、遺品整理、遺産分割は、故人の死後に残された品物や財産に関わる手続きですが、それぞれ目的と対象が異なります。
形見分けは、故人が愛用していた品や思い出の品を、遺族や親しい人に分け与える行為です。これは故人を偲び、思い出を共有することを目的としており、主に財産的価値の低いものが対象となります。
一方、遺品整理は、故人の持ち物すべてを整理する作業全般を指します。不用品の処分や形見分け品の選定も含まれます。
遺産分割は、故人の所有していた財産(現金、不動産、株式など)を、民法で定められた相続人(法定相続人)で分割することを指します。形見分けとは異なり、財産的価値のあるものが対象となり、法的な手続きが必要です。
したがって、形見分けは故人を偲ぶための慣習であり、遺品整理はその過程で行われる作業、遺産分割は法に基づいた財産の分配という違いがあります。
高価な品物は形見分けではなく遺産分割の対象となる場合があるので注意が必要です。
→あわせて読みたい
「遺品整理と不用品回収の違いはなに?|メリット・デメリットを解説」
形見分けのタイミング
形見分けをするタイミングは、信仰する宗教によって異なります。
仏教:49日後
形見分けのタイミングに厳密な決まりはありませんが、一般的には四十九日法要の後に行われることが多いです。これは、仏教において四十九日が「忌明け」にあたり、遺族が日常生活に戻る区切りのためです。
神式:五十日祭もしくは三十日祭の後
仏教での「忌明け」は、神道では五十日祭または三十日祭と呼ばれます。この時期に形見分けを行うことが多いようです。
キリスト教:一ヶ月命日の追悼ミサ以降
キリスト教には形見分けという概念はありませんが、故人を懐かしむ品を配る際には一ヶ月命日の追悼ミサの後になることが多いようです。
これらの形見分けのタイミングは「絶対」ではありません。故人が亡くなったショックで何も手に着かず、遺品整理に時間がかかることもあります。故人の遺言がある場合は別ですが、そうでなければ遺されたご家族が「分けてもいいかな」と思うタイミングを待ちましょう。
→あわせて読みたい
「四十九日前に遺品整理しても大丈夫?|メリットや疑問点を解説」
どんな品物を形見分けする?

形見分けは、故人が日常で使っていた品や収集していた品を分けるのが一般的です。具体的には、時計・財布などの日用品や装飾品・服などの衣類、着物や蔵書・釣り道具などの趣味の品です。
日ごろ愛用していた品物は「故人を思い出して欲しい」「故人の思い出と一緒にいて欲しい」という思いから形見分けする方が多いようです。
趣味の品物は「まだまだ使えるし、もっと故人も遊びたかっただろうから」という思いから、第三者に譲渡することもあります。また「故人は着物が好きだったけれど、自分は興味がないから」と遺族では活用できないものを同じ趣味を持つ方に使ってもらうという場合もあります。
→あわせて読みたい
「遺品整理で食器を片付ける方法|処分の仕方を徹底解説」
「遺品整理で出た宝石の処分方法は?|売る・リフォームする方法と注意点をご紹介」
「遺品整理で出てきた印鑑の処分方法6つ。実印の有効期限も解説」
形見分けのマナー

内々で行われることの多い形見分けですが、マナーがあります。具体的に見ていきましょう。
目上の人には形見分けしない
形見分けは本来、親から子、上司から部下に贈られるものなので、目下から目上の人に形見分けするのは失礼だと言われています。しかし、昨今では昔ほど上下関係の隔たりがなくなりました。
仮に上下関係があっても、親しかった人に渡したい場合には失礼を詫びた上で打診してみましょう。
包み紙にいれない
形見分けの品物はプレゼントではないので、ラッピングは不要です。代わりに、クリーニングしたりメンテナンスしてから渡しましょう。
どうしても何かに包みたい場合には、半紙のような白い紙に包みましょう。仏式なら「遺品」、神式なら「偲ぶ草」と表書きするのがマナーです。
また、遠方に住んでいて直接渡せない場合には、破損しないようきちんと梱包しましょう。
新品を用意しない
「故人が使った中古品を渡すなんて気が引ける」と時々新品を用意する人がいますが、それでは形見分けの意味がありません。
故人が愛用した品をお渡しすることで、故人を偲んでいただくのが形見分けの目的です。
あまりに汚れが気になるのなら、形見分けの品から外すか、クリーニングなどで対応しましょう。
品物をきれいにしてから渡す
形見分けをする際は、単に故人の品物を手渡すのではなく、感謝の気持ちを込めて丁寧な準備をすることが大切です。
品物を贈る前に、ほこりを拭いたり、洗濯やクリーニングをしたりして、できる限りきれいな状態にしましょう。これにより、受け取った方が気持ちよく故人を偲ぶことができます。
品物によっては、専門業者によるメンテナンスが必要な場合もあるので、品物の種類に応じて適切な対応を検討しましょう。
形見分けの注意点

形見分けする際のマナーをご紹介しましたが、これ以外に注意すべき点もあります。マナーをクリアしていても、注意点を忘れると思わぬトラブルに発展しかねません。事前に押さえておきましょう。
形見分けは相手が喜ぶものを
形見分けは不用品の処分ではありません。いくら故人が愛用していた品物でも、相手によってはいらない場合もあります。事前にきちんと打診しましょう。
税金の発生に注意
形見分けは遺品を親族や生前の友人に分ける行為で、一般的に価値の低い(もしくはない)ものを対象としています。そのため、相続税や贈与税は基本的に発生しません。ただし、形見分けしたものが実は高価だった場合には、遺産分割の対象とみなされ、税金が発生することもありえます。絵画や宝石など一見して価値がわかりにくいものは、専門家に確認してもらうのも手です。
とはいえ、仮に第三者に贈与する場合であっても、1年間の贈与の価額の合計額が110万円以下なら贈与税は発生しませんのでご安心ください。
[参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
現金やペットは避ける
故人が生前飼っていたペットを形見分けとして譲り渡すことは、相手の負担となる可能性があるため避けるべきです。事前に相手の状況をよく確認し、難しい場合は他の方法を検討しましょう。
また、現金や金券、換金性の高いものも、遺産分割の対象となるため形見分けには適していません。これらの品は、相続財産として適切に処理する必要があります。
形見分けのよくある質問
形見分けに関してよくある質問をまとめました。これらの情報を参考に、故人を偲ぶ大切な形見分けを円滑に進めてください。
生前に形見分けはできる?
生前でも形見分けをすることは可能です。
近年、終活の一環として生前に形見分けをする方が増えています。これは、認知症になったり病気で入院したりすると、思い通りに形見分けができなくなる可能性があるためです。生きている間に形見分けをすることで、誰にどの品物を贈るか自分の意思を反映させられます。
また、本人が直接渡すため、形見をめぐる親族間でのトラブルを防ぐ効果も期待できます。ただし、高価な品物を生前贈与として渡す場合は、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。
形見分けする人がいない時は?
「まだ使えるものだけど、引き取り手がいない」
「価値のあるものだから、捨てるには忍びない」
「誰かに使ってもらいたい」という希望がある場合には、品物によっては引き取ってもらえることもあります。
例えば蔵書であれば図書館に寄贈できたり、着物であればリサイクルに出したりなどです。意外なところでは、昭和のビデオ(VHS)や家電も歴史の資料として引き取ってくれるところもあります。「こんなものは買い取ってもらえないのでは」と思っても、一度調べたり問い合わせをしてみましょう。
引き取り手を探すのが面倒な場合は、私たちおうち整理士にお任せください。亡くなった方の遺品整理はもちろん、遺品買取も実施しておりますので、お客様が大切にされている形見も経験豊富なスタッフが1点ずつ丁寧に査定いたします。査定したお品物はそれを必要とする人の手に渡るため、処分に抵抗がある人でも安心してご利用いただけます。
10秒で相場がわかる無料見積もりも実施していますのでぜひご利用ください。
【簡単】10秒で完了!
まとめ
故人を偲ぶ品物を親しい人達に分ける形見分け。実は適した時期やマナーがあります。心の整理がついたら、この記事を参考に形見分けをしてみてください。

これまでにおうち整理士で700件以上の遺品整理を担当。特殊清掃、リフォーム、骨董品買取など幅広い経験を重ねた上で知識を取得し、お客様に寄り添った仕事をモットーとしている。一般社団法人 遺品整理士認定協会「遺品整理士」を所持。