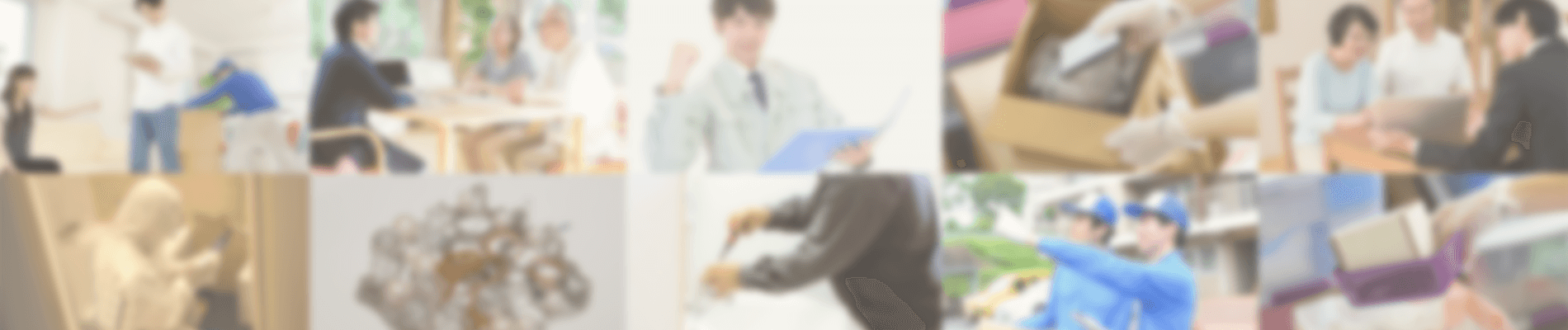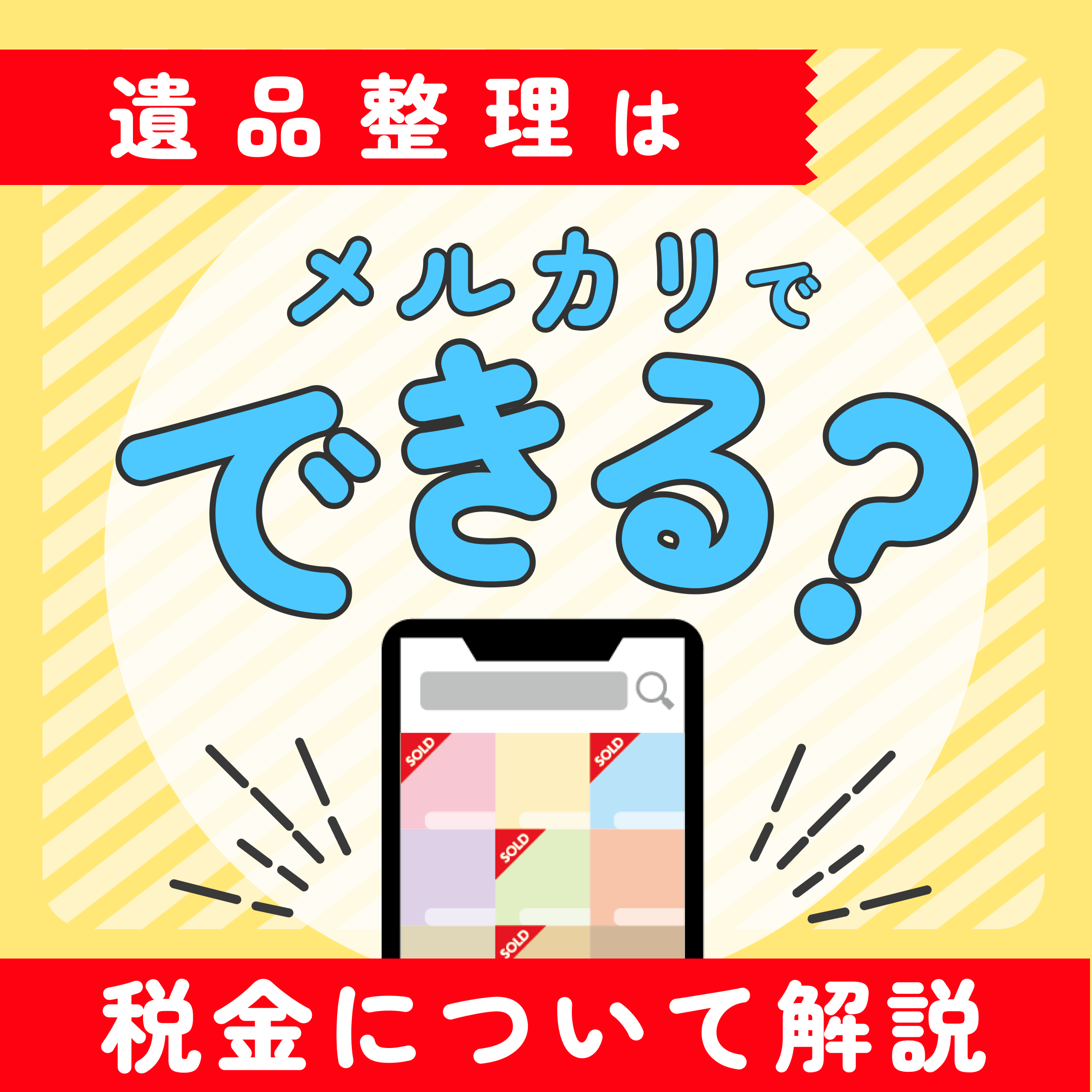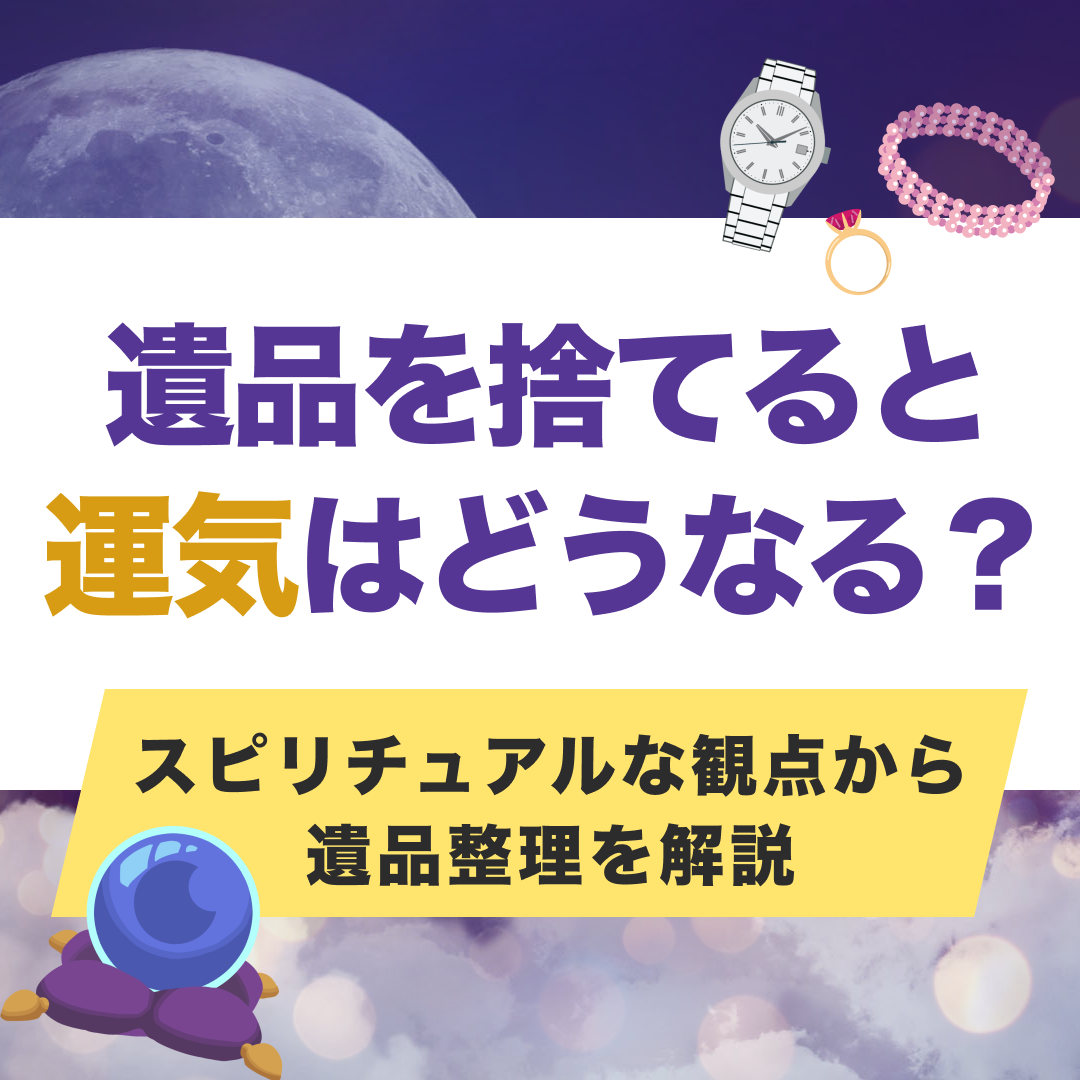遺品整理に慶弔休暇は利用できる?|取得要件や忌引休暇との違いを解説
![]() 最終更新日:2025.07.03
最終更新日:2025.07.03
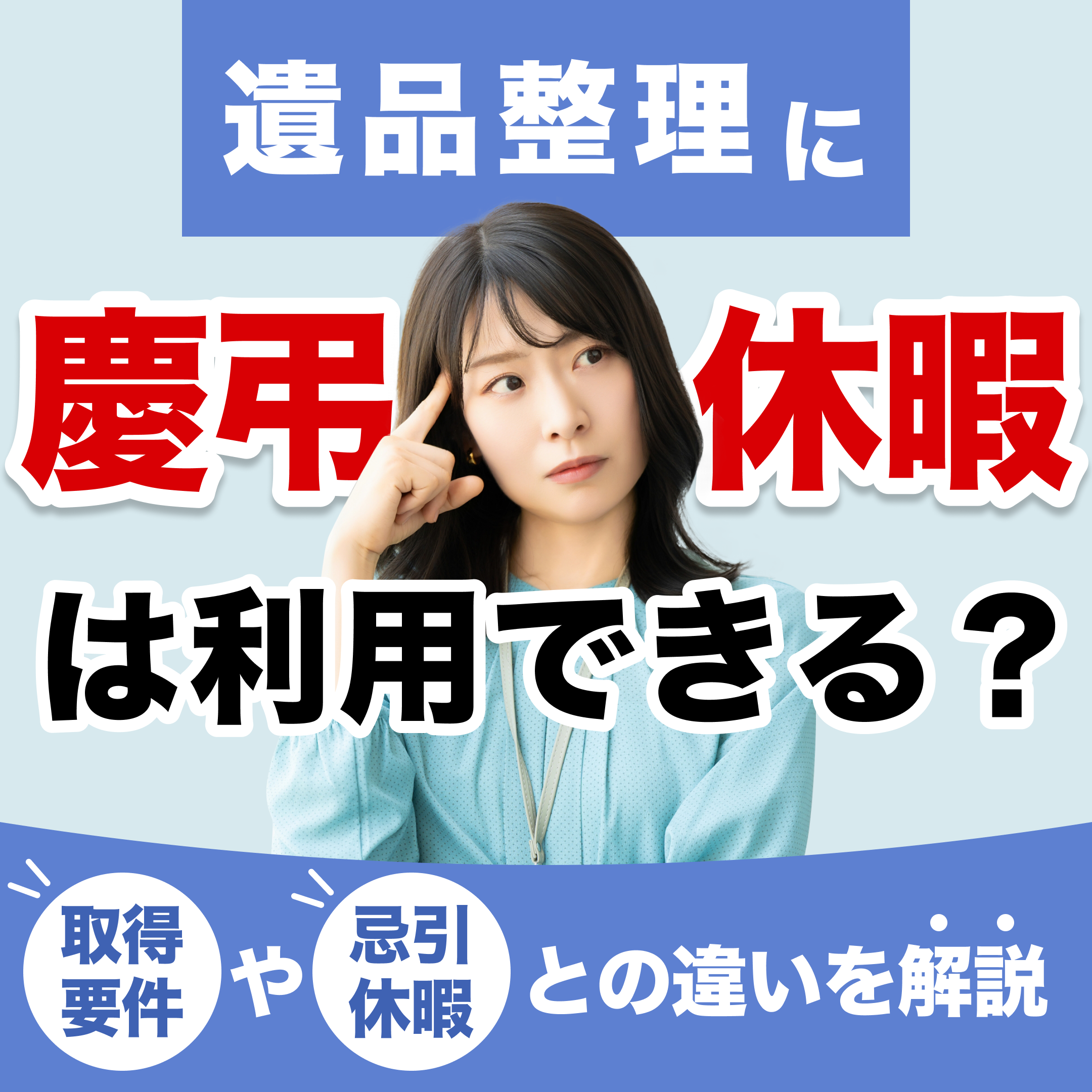
身近な人が亡くなった際、葬儀や各種手続きに加え、遺品整理も行う必要があります。
仕事と並行してこれらの作業を進めるのは、心身ともに大きな負担となることも少なくありません。
このような状況で利用を検討するのが「慶弔休暇」ですが、遺品整理を理由に取得できるのか、忌引休暇との違いは何なのか、疑問に思う方もいるかもしれません。
本記事では、遺品整理における慶弔休暇の利用について、その理由や取得条件、忌引休暇との違い、具体的な進め方などを詳しく解説します。

こんにちは。おうち整理士の榛田(はりた)です。今回は、慶弔休暇を使った遺品整理や遺品整理の適切なタイミングについてご紹介します。
目次
慶弔休暇ってどんな制度?

慶弔休暇とはどのような制度なのか、解説していきます。
慶弔休暇の定義と一般的な内容
慶弔休暇は、従業員自身やその近親者において、結婚、出産、死亡といった慶事や弔事があった際に取得できる、会社独自の休暇制度です。
これは労働基準法で定められた休暇ではなく、企業が福利厚生の一環として就業規則に規定する「特別休暇」となります。
一般的には、対象となる慶事・弔事の範囲や、それに応じた取得可能日数が定められています。
多くの企業で導入されており、労働政策研究・研修機構の2020年の調査では、94.9%の企業が慶弔休暇制度を設けているという結果があります。
しかし、取得条件や休暇中の給与(有給か無給か)の扱いは会社によって異なるため、自社の就業規則を確認することが重要です。
慶弔休暇の法的な位置づけ
慶弔休暇は、労働基準法で定められた年次有給休暇のような「法定休暇」とは異なり、企業が任意で設ける「特別休暇」に位置づけられます。
法律で定められた制度ではないため、企業に導入の義務はなく、休暇を付与するかどうか、またその内容(対象となる事由、日数、有給・無給など)は各企業の就業規則に委ねられています。
しかし、多くの企業では従業員の福利厚生として導入しており、就業規則に明記することでその効力が発生します。
忌引休暇と慶弔休暇の違い
慶弔休暇と忌引休暇は、どちらも身内の不幸に関連して取得できる休暇ですが、その性質や対象となる範囲に違いがあります。
忌引休暇の定義
忌引休暇(きびききゅうか)、あるいは一般的に忌引きと呼ばれる休暇は、従業員の家族や親族が亡くなった際に、葬儀への参列やそれに伴う手続きを行うために取得できる休暇です。
広義には慶弔休暇の一部として位置づけられることが多く、特に弔事に特化した休暇と言えます。
忌引は、近親者の死に際して一定期間喪に服し、身を慎むという日本の習慣に由来しています。
取得できる日数や対象となる親族の範囲は、慶弔休暇と同様に会社の就業規則によって定められています。
二つの休暇制度の主な相違点
慶弔休暇と忌引休暇の主な違いは、対象となる出来事の範囲にあります。
忌引休暇が親族の不幸、すなわち弔事に限定されるのに対し、慶弔休暇は慶事(結婚や出産などのお祝い事)と弔事の両方を対象としています。
したがって、忌引休暇は慶弔休暇の一部であると言えます。
また、多くの企業で忌引休暇は有給とされることが多いですが、慶弔休暇においては慶事の内容によっては無給となる場合もあります。
遺品整理で慶弔休暇を利用するための条件
ここからは、遺品整理に慶弔休暇を利用する条件を解説していきます。
遺品整理を理由に取得できる可能性
慶弔休暇は主に葬儀や法要への参列を目的とした休暇ですが、会社の就業規則によっては遺品整理を理由として取得できる可能性もゼロではありません。
特に、故人が遠方に住んでいた場合や、遺品整理に多くの時間を要する場合など、葬儀や法要に付随する作業として遺品整理が含まれると解釈されることがあります。
ただし、遺品整理自体を慶弔休暇の取得理由として明確に認めている会社は多くないため、事前に会社の規定を確認し、人事担当者や上司に相談することが不可欠です。
遺品整理の必要性や、なぜその期間に休暇が必要なのかを具体的に説明することが重要になります。
対象となる親族の範囲も会社によって異なるため、これも確認が必要です。
慶弔休暇が利用できない場合の代替手段
慶弔休暇の取得が難しい場合や、付与された日数だけでは足りない場合は、他の休暇制度との併用を検討する必要があります。
最も一般的な代替手段は、年次有給休暇を利用することです。慶弔休暇と組み合わせて取得することも可能で、企業によっては、リフレッシュ休暇や特別休暇など、他の目的で利用できる休暇制度がある場合もあります。就業規則を確認してみましょう。
また、育児休暇や介護休暇のように、特定の家族状況に対応した休暇制度が利用できる可能性も考慮に入れられますが、遺品整理に直接適用できるかは会社の規定によります。
どうしても時間がない場合は、遺品整理業者に依頼することも有効な代替手段となります。
業者に依頼すれば、専門知識を持つスタッフが効率的に作業を進めてくれるため、限られた時間でも遺品整理をスムーズに進められますよ。
→あわせて読みたい
「遺品整理を業者に依頼するメリット6つ|どんな業者を選ぶと良いかも解説」
慶弔休暇の取得日数について

慶弔休暇の取得日数は、会社の規定や故人との関係性によって変動します。
対象者と取得日数の目安
慶弔休暇における弔事の場合の取得日数は、亡くなった方と従業員本人との続柄によって日数の目安が定められているのが一般的です。
- 配偶者:10日程度
- 父母:7日程度
- 子ども:5日程度
- 祖父母や兄弟姉妹、配偶者の父母:3日程度
孫や叔父、いとこなど、関係性が遠くなるにつれて日数は短くなる傾向にあり、1日程度や、会社によっては取得の対象外となる場合もあります。
これらの日数はあくまで一般的な目安であり、実際の対象者と取得可能日数は会社の就業規則によって異なります。
また、遠方で葬儀を行う場合など、移動にかかる日数が考慮されるケースもあります。
3親等以遠の親族の場合
慶弔休暇の対象となる親族の範囲は、会社によって異なりますが、一般的に3親等以遠の親族の場合、忌引休暇の対象とならないことがあります。
3親等にあたる親族の例としては、曽祖父母やおじ・おばなどが挙げられます。
これらの親族が亡くなった際に慶弔休暇が取得できるかどうかは、企業の就業規則の範囲内で個別に定められています。
会社によっては、3親等以遠の親族の弔事に対しても1日程度の休暇を認めるケースや、全く認めないケースなど様々です。
したがって、3親等以遠の親族の遺品整理のために休暇を検討する場合は、必ず事前に会社の就業規則を確認するか、人事担当者に問い合わせて、ご自身の会社の規定の範囲内であるかを確認しましょう。
喪主の場合の日数について
忌引休暇の日数は、故人との関係性によって異なりますが、特に喪主を務める場合は、葬儀の準備や各種手続きに時間を要するため、通常よりも長く休暇が設定されていることがあります。
例えば、父母が亡くなり喪主を務める場合は、一般的な7日間よりも長い日数が付与されるなど、会社の規定によって日数が増えることがあります。
これは、喪主が葬儀の中心となって様々な対応を行う必要があるためです。
具体的な喪主の場合の日数は、会社の就業規則に定められているため、必ず確認するようにしましょう。
慶弔休暇を申請する際の伝え方
慶弔休暇を申請する際は、会社への適切な伝え方が重要です。
必要な情報を正確に伝え、円滑に休暇を取得できるようにしましょう。
会社への申請方法と伝えるべき内容
慶弔休暇を会社に申請する際は、まず直属の上司に口頭で連絡を入れるのが一般的です。
その際に伝えるべき内容は、休暇が必要な理由(誰が亡くなったのか、故人との関係性)、必要な期間(何日から何日まで)、そして可能な範囲で葬儀の日程や場所などが挙げられます。
その後、会社の規定に沿って正式な申請手続きを行います。
申請方法としては、社内の申請書に記入して提出する場合や、システム上で申請を完了させる場合などがあります。
会社によっては、故人との関係性や死亡の事実を証明するために、死亡診断書や会葬礼状などの書類の提出を求められることがありますので、事前に確認しておくとスムーズです。
申請時は、休暇が必要な具体的な理由と期間を明確に伝え、必要な手続きについて確認しましょう。
休暇中の業務引き継ぎについて
慶弔休暇を取得する際は、休暇中に担当している業務について、事前にしっかりと引き継ぎを行うことが重要です。
急な休暇となる場合でも、可能な範囲で業務の状況や緊急連絡先などを整理し、同僚や関係部署に伝えておきましょう。
具体的な引き継ぎ内容としては、現在進行中のプロジェクトの進捗状況、対応が必要な顧客や取引先、使用中の資料やデータの場所などが挙げられます。
口頭での説明に加え、引き継ぎ資料を作成しておくと、休暇中の担当者が困らずに済みます。
また、緊急時の連絡先を伝えておくことで、やむを得ない状況での確認や対応が可能となります。
円滑な業務遂行のため、責任をもって引き継ぎを完了させましょう。
遺品整理を開始する適切な時期

慶弔休暇で遺品整理を始める際、適切なタイミングを選べば効率よく進められます。事前に確認しておきましょう。
四十九日
遺品整理を始める一般的なタイミングとしては、葬儀や告別式といった一連の儀式が終わり、少し落ち着いてから取り掛かる方が多いです。
特に、仏教においては故人が亡くなってから49日目にあたる四十九日法要を目安とする考え方があります。
これは、四十九日をもって故人の魂が次の世界へ旅立つとされる重要な区切りだからです。
四十九日法要の後で遺品整理を行うことで、故人を偲びながら落ち着いて作業を進めることができると考えられています。
ただし、これはあくまで一般的な目安であり、一周忌やそれ以降の法要、あるいは遺族の気持ちの整理がついたタイミングで行うこともあります。
→あわせて読みたい
「四十九日前に遺品整理しても大丈夫?|メリットや疑問点を解説」
四十九日前でも問題ない
遺品整理を四十九日前に進めることに、宗教上の明確なタブーはありません。
遺品整理を行う時期に法的な定めもないため、四十九日前に行っても問題はないとされています。
むしろ、賃貸物件の明け渡し期限がある場合や、相続に関する手続きを急ぐ必要がある場合など、四十九日を待たずに遺品整理に着手する必要があるケースもあります。
四十九日前に遺品整理を行うことで、忌引休暇などを活用して集中的に作業を進められるというメリットもあります。
ただし、遺族の中には四十九日までは故人の魂が家に留まっていると考える方もいるため、関係者間でよく話し合い、理解を得てから進めることが大切です。
急ぎの対応が必要なケース
遺品整理において急ぎの対応が必要となるのは、いくつかの具体的なケースが考えられます。
最も一般的なのは、故人が賃貸物件に住んでおり、契約期間が決まっている場合です。このような場合は速やかに遺品整理を行い、物件を明け渡す手続きを進める必要があります。
また、故人の事業に関する書類や、税金関係の手続きに必要な書類が遺品に含まれている場合も、期限が定められていることが多いため、早期に確認・整理が求められます。
その他、貴重品や重要書類の所在が不明な場合や、遺品の量が多くて個人での対応が難しい場合なども、専門業者に依頼するなどして早めに対応を開始する必要が生じます。
遺品整理を進める上での注意点
遺品整理は単に物を片付ける作業だけでなく、故人の思い出の品や財産に関わるものも含まれるため、いくつかの重要な注意点があります。
他の親族との合意形成
遺品整理は故人の財産や思い出の品に関わるため、トラブルを防ぐためには他の親族との間で事前にしっかりと合意形成を図ることが非常に重要です。
特に、遺品の分け方(形見分け)や処分方法については、親族間で意見が分かれることがあります。
誰がどの遺品を相続するのか、価値のあるものはどうするか、不用品をどのように処分するかなど、遺品整理の範囲や方針について、関係者全員が納得できるまで十分に話し合いましょう。
感情的にならず、故人を偲びながら協力して進める姿勢が大切です。
遺言書やエンディングノートの確認
遺品整理を開始する前に、故人が遺言書やエンディングノートを残していないか必ず確認することが重要です。
これらの書類には、財産の分配方法や希望する葬儀、遺品整理に関する指示などが記されている場合があります。
遺言書の場合は法的な効力を持つため、内容に従って遺品整理を進める必要があります。
エンディングノートに法的拘束力はありませんが、故人の意思を知る手がかりとなります。
これらの書類を見落として遺品整理を進めてしまうと、後々トラブルになる可能性もあります。
特に金銭や貴重品に関する指示が記載されていることもあるため、慎重に確認を行いましょう。
相続放棄を検討している場合
遺品の中に借金などの負の財産が含まれている可能性があり、相続放棄を検討している場合は、遺品整理の進め方に特に注意が必要です。
相続放棄をする場合、故人の財産を一切相続しない旨を家庭裁判所に申請する必要があります。誤って遺品を整理したり処分したりすると「相続の単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があるためご注意ください。
相続放棄を検討している場合は、遺品に手を付ける前に、まず弁護士などの専門家に相談し、今後の手続きについて指示を仰ぐようにしましょう。
重要な手続きに関わるため、自己判断で遺品整理を進めないことが賢明です。
→あわせて読みたい
「相続放棄しても大丈夫?遺品整理の前に確認しておくべきことを解説」
まとめ
遺品整理に慶弔休暇(忌引休暇)を利用できるかどうかは、会社の就業規則によって異なります。
遺品整理は故人を偲ぶ大切な機会であると同時に、様々な手続きや作業が伴います。
計画的に進めるためにも、会社の制度を理解し、必要に応じて休暇制度を有効活用しましょう。
わたしたちおうち整理士でも遺品整理を行なっています。お客様に寄り添い、親身になってお話を聞かせていただきます。遺品整理士も在籍しているため安心してお任せいただけますよ。
お見積り
出張費
キャンセル
0円
即日お見積り&作業!実績多数!
まずはお気軽にお電話ください。
通話無料!営業時間 9:00~19:00/年中無休
![]() 0120-769-737
0120-769-737

![]() 受付時間外はメールでご相談ください
受付時間外はメールでご相談ください
[ 24時間365日受付 ]メールで相談する

これまでにおうち整理士で700件以上の遺品整理を担当。特殊清掃、リフォーム、骨董品買取など幅広い経験を重ねた上で知識を取得し、お客様に寄り添った仕事をモットーとしている。一般社団法人 遺品整理士認定協会「遺品整理士」を所持。